- recommend
自転車での通勤時の事故は労災になるのか?

通勤中に自転車で事故に遭った瞬間、「これって労災になるの?」と頭をよぎったことはありませんか。
会社への報告の仕方や申請の手順がわからず、もし認定されなかったら治療費や休業中の収入はどうなるのか…そんな不安がいっきに押し寄せてきますよね。さらに、自転車通勤自体を会社に申請していない人も多く、「届け出していないのに申請できるのかな」と迷う場面もあるでしょう。
この記事では、通勤中の自転車事故が労災になる条件をわかりやすく整理し、認定されやすいケースとそうでないケースを現実的な事例で紹介します。
通勤中の自転車事故は労災になるの?認定される条件と申請手順

通勤中に自転車で事故を起こしたとき、「自分の場合、労災になるのか」がまず気になりますね。普段通る道か、寄り道があったかどうかなど、条件が少し変わるだけで認定可否が変わります。
ここでは、実際の事故データや事例を交えて、認定される場合とされない場合を明確にし、そのあとで「もし認定されるなら何をすればいいか」を順を追って説明します。
最新データから見る事故の発生状況 📊
| 警察庁の「自転車事故の発生状況」によれば、平成20年度には自転車を使用中の死傷者数が約162,525件で、交通事故全体の約21.2%を占めていました。 |
参考元:日本の人事部
| 警察庁の「自転車事故の発生状況」によれば、平成20年度には自転車を使用中の死傷者数が約1同じく平成21年度には、「自転車が当事者となった交通事故」が156,373件発生し、交通事故全体の約21.2%という数字が出ています。死亡事故も含まれ、692人が死亡しました。 |
参考元:労務ドットコム
また、国の「自転車を巡る現状等」資料では、ここ10年で自転車関連事故件数はおよそ半分に減少しているが、自転車乗車中の死亡者数が減少してもその割合が高いこと、歩行者との事故は減少せずほぼ横ばいであることなどが報告されています。
参考元:国土交通省
自転車での通勤中の事故が労災認定されるケースとされないケース
| 状況 | 認定される可能性 | 実際の例 | なぜその判断になるか |
|---|---|---|---|
| 自宅→会社の最短ルートを通勤中、信号待ちで青になり発進中に自動車と接触 | ◎ 認定される可能性大 | 普段使っている道で、自転車道あり、信号あり。 | 通勤の往復かつ合理的な道・時間・交通手段。中断・寄り道なし。 |
| 自宅→保育園→会社というルートで保育園への立ち寄りあり | ◎ 認定される可能性大 | 保育園が近く、毎朝同じ順序で行ってから会社に行く。 | 保育園送迎など日常生活上必要な立ち寄りは合理的とされることがある。 |
| 雨のため少し遠回りする道を使っていたが事故発生 | △ ケースによる | 普段使っていない迂回ルート。道が滑りやすかった。 | 天候などやむを得ない理由で行き先やルートを変える場合、合理的と判断される余地あり。証拠があると尚良い。 |
| 通勤途中にランチを買いに店に寄った→出て自転車で転倒 | △〜✕ 認定されにくい | 店の場所が通勤路沿いであっても、目的が私的用事。 | 通勤と関係ない寄り道は「中断・逸脱」とされやすく、その後の事故は認められないことが多い。 |
| 友人に会うため途中で立ち止まり、会話後に帰る途中で事故 | ✕ 認定されない | 通勤とは無関係な行動。 | 通勤の定義から外れ、認定対象にならない。 |
- 合理的な経路かどうかが最大のポイント
「合理的な経路」とは、普段から使っているルート・最短または安全なルートを指します。多少の遠回りでも、渋滞を避ける・危険な交差点を回避するなど合理的理由があれば認められることがあります。 - 寄り道が必ずアウトとは限らない
保育園や幼稚園への送迎、公共交通機関への乗り継ぎ、忘れ物を取りに帰るなど「日常生活上必要な行為」であれば例外として認定されることがあります。 - 証拠の有無が認定を左右する
事故現場の写真・警察への事故届・病院の診断書・通勤ルートの地図など、後から客観的に証明できる資料を残しておくと認定されやすくなります。 - 会社への報告が重要
会社が労基署への提出書類を作成するケースが多いため、事故当日に必ず報告しましょう。「報告が遅れたせいで認定が遅れた/認定されなかった」という例もあります。 - 就業規則に自転車通勤の記載がなくても申請可能
会社が自転車通勤を認めていない場合でも、法律上は「就業のための合理的な通勤」であれば認定される余地があります。ただし、会社とトラブルにならないよう事前に申請しておくと安心です。 - 天候や交通事情によるルート変更も記録を残す
雨天や工事で迂回した場合、普段のルートと違うことを説明できるようにメモやスクリーンショットを残しておくと有効です。
認定されると判断できたら:申請の7ステップ
事故後に冷静に動けるよう、やるべきことを順番に整理しておきます。
- 1.事故直後の状況を記録する
- 場所・日時・天候・交通状況・信号・見通し・その他状況。スマホで写真を撮る。自転車の損傷も撮影。見えないケガについても医師に伝える。
- 2.第三者の証言をとり、警察へ届出を出す
- 可能な限り目撃者を探し、連絡先を控える。第三者の証言は後で有効になることがあります。またすぐに警察に届け出を出すことも忘れないようにしてください。
- 3.会社へすぐに報告する
- 上司または総務・人事・労務担当に。「通勤中の事故である」「普段使うルートであった」「自転車通勤である」ことを口頭と可能であれば書面で知らせる。
- 4.病院を行き、治療および診断書を取得
- 「通勤中に自転車で事故にあった」という事情を医師に伝え、診断書に記載をお願いする。
- 5.必要な書類を揃える
- 通勤経路を示す地図または写真、住所・会社名・勤務先・通勤開始時刻など、事故報告書・診断書・休業があれば休業証明書など。
- 6.労働基準監督署への申請
- 会社を通じてまたは本人が申請可能。手続きに不備がないように。
- 7.給付内容を確認する
- 治療費の支給、休業補償、後遺障害がある場合の給付など、それぞれどの程度支払われるか。
会社に届け出ていないから労災はムリ??
「会社に届け出ていないから労災はムリだろう」「寄り道してたら“通勤”とは言えない」という声はよくありますが、それぞれ対策が可能です。
自転車通勤の労災リスクの実態と会社に申請すべきかどうかの判断基準

自転車通勤がリスクかどうかをデータで確認すると、実際の事故率や企業の対応態度が見えてきます。そうすると、自分が申請すべきかどうかの判断もしやすくなります。
企業/公共データから見える傾向
| 「自転車を巡る現状等」の資料で、ここ10年で自転車関連事故件数は約50%減少している一方、自転車乗車中の死亡者数の割合は減少しても、全交通事故に占める割合が高めに維持されているという報告があります。 |
参考元:国土交通省
| 「自転車の利用に係る企業行動調査アンケート(令和5年)」では、自転車通勤を認めていない企業のうち、81.8%が「交通事故の懸念」を理由としており、企業側でも自転車通勤の安全リスクをかなり意識しているという結果が出ています。 |
| 東京労働局の情報によれば、「合理的な経路及び方法」「住居と就業との間の往復」などが法令上の通勤災害の要件として明記されており、通勤時の交通手段として自転車が合理的な方法として扱われうることが制度上認められています。 |
参考元:通勤災害について
これらのデータから、自転車通勤は確かに事故リスクを伴うものの、制度としてカバーされる可能性が十分にあることがわかります。
労災申請すべきかを見極める5つの質問
以下の質問を自分に投げかけてみることで、「自転車通勤を申請すべきかどうか」がかなりクリアになります。
普段使っている通勤ルートか
→ いつも同じ道を使っているなら、合理的な経路として認められやすい。
自宅⇔会社間の移動か、会社指定の他の就業場所との移動か
→ 通勤災害の定義に合っていれば申請の可能性あり。
途中で私用の寄り道や中断がないか
→ 最小限度の立ち寄りは例外として認められるが、私的な寄り道が頻度高くあると認められにくい。
会社に自転車通勤が許可または黙認されているかどうか
→ 許可制でなくても黙認されている事実や、会社が自転車通勤者に配慮をしているかどうかが後で申請の際に有利。
事故の証拠を揃える準備ができるか
→ 写真・目撃者・診断書など、事故後に状況を証明できるものがあれば申請成功率が上がる。
この中で多数「はい」があれば、会社に申請することをおすすめします。
無申請・隠して通勤していた場合のリスク
自転車通勤を会社に申請せずに続けていると、万が一事故が起きたときに思わぬ不利益を受ける可能性があります。まず大きいのは、医療費や通院費がすべて自己負担になるケースです。
また、健康保険で先に診療を受けたあとで「やっぱり通勤災害だった」と主張すると、保険者から費用の返還を求められることもあります。結果的に二重手続きとなり、精神的にも負担が大きくなります。
さらに、会社に報告していなかったことで「通勤状況を隠していた」と見なされ、職場との信頼関係に影響するケースも少なくありません。
このように、無申請での自転車通勤は「事故が起きなければ問題ない」と思われがちですが、ひとたびトラブルになると経済的にも精神的にも大きな負担がかかります。あらかじめ会社に通勤手段を申請し、通勤経路を明確にしておくことで、事故後の補償や手続きがスムーズになり、安心して通勤を続けることができます。
自転車での通勤時の労災・・もし労災が認められなかったら治療費や休業はどうなる?

「もし労災が認められなかったら、治療費は? 仕事を休んだ間の収入は? 家計にどれくらい響く?」――頭の中でいくつもの疑問がぐるぐる回って、落ち着かない気持ちになりますよね。しかも“自転車通勤は自己責任なんじゃないか”とまわりに言われることもあり、余計に不安が強くなりがちです。
ここではそのモヤモヤを、ひとつずつ“見える化”します。まずはあなた自身の“備え”を確認するところから始めましょう。
まずお聞きします。あなたは今、どんな保険に入っていますか?
下のチェック項目を、心の中で「✅はい/❌いいえ」で答えてみてください。
□健康保険(協会けんぽや組合健保)に加入している
□個人の傷害保険(ケガの入院・通院をカバーするタイプ)に入っている
□いわゆる“自転車保険”(相手への賠償や自身のケガ補償がセットのもの)に入っている
□個人賠償責任保険(他人にケガをさせた・物を壊した時の賠償)に入っている(火災保険やクレカに付帯していることも多い)
□休業補償(就業不能)タイプの保険に入っている
□後遺障害に備える保険に入っている
「はい」が多いほど、万が一“労災が不認定”でもダメージを小さくできる可能性が高まります。逆に「いいえ」が多ければ、これを機に“どれを優先して備えるか”を決める材料にしてください。
ここからは、通勤中の自転車事故で“労災が認められなかった場合”に、現実的にどの保険がどこまで助けてくれるのか?を改めてご紹介します。自分の加入状況と照らして、足りないところを見つけていきましょう。
どの保険がどこまで助けてくれるのか
| 保険の種類 | あなた自身の治療費 | 休業(収入減) | 相手への賠償 | 特徴・見落としがちな点 |
|---|---|---|---|---|
| 健康保険 | ○(自己負担あり) | ×(基本なし) | × | もっとも確実な土台。労災不認定なら通常の医療として扱われ、自己負担分は発生。長引くと支出がかさむ。 |
| 傷害保険(個人) | ○(通院・入院・手術など) | ○/△(特約次第) | × | 自分のケガを手厚くカバー。通勤中を補償対象に含むか、支払条件(通院何日以上など)を要確認。 |
| 自転車保険(パッケージ) | △/○(商品による) | △(商品による) | ○(高額賠償にも対応のことが多い) | 「個人賠償+傷害」をセットにしたタイプが主流。通勤利用が対象か、補償上限はいくらかを確認。 |
| 個人賠償責任保険 | × | × | ○(対人・対物の賠償) | 自分の治療費は出ないが、相手への賠償を強力にカバー。火災保険・自動車保険・クレカ付帯に潜んでいること多数。 |
| 就業不能(休業)保険 | × | ○(働けない期間の収入を補填) | × | 会社経営やフリーランスなら優先度が高い。待機期間や“どの状態を就業不能と定義するか”を必ず確認。 |
| 後遺障害(後遺症)保険 | △(後遺障害等級で一時金) | △ | × | 後に生活が変わるレベルの障害に備える“最後の砦”。対象となる後遺症の範囲や給付額を要チェック。 |
ポイント
では、実際に不認定になりやすい“境界線”はどこにあるのか。ここからは一次情報・実例で、リアルな線引きを確認します。
厚生労働省/東京労働局の公式解説では、通勤途上の「逸脱(合理的経路からそれる)」「中断(経路上で通勤と無関係な行為)」があるとその間およびその後は原則「通勤」と認められず、労災の対象外になります。一方、“日常生活上必要な最小限の行為”(例:日用品購入、医療機関受診、投票など)は例外として扱われ、合理的な経路に復した後は再び通勤として認められます。
参考元:通勤災害について
実際の不認定事例:出勤途中にコンビニで買い物をするため店内に立ち寄り、店内で転倒して負傷したケース。裁判所は、コンビニ店内は管理者の支配する“私的な空間”で、買い物という目的自体が通勤の移動と異なるとして、通勤の逸脱・中断に当たり不支給と判断しました。
参考元:通勤中に立ち寄ったコンビニで転倒して負傷した場合の労災請求
これらを読むと、“店の敷地に入るか否か”、“行為の目的が通勤か私用か”、“最小限の行為かどうか”が、認定/不認定の分岐点になっていることが、肌感覚でつかめるはずです。
「労災が不認定だった」とき、どれほどの負担があるのか?
ここからは、「労災が不認定だった」ときに本当に困るお金の動きを、少しだけ“生活目線”でイメージしてみましょう。
- 治療費:健康保険で自己負担が発生。通院が長期化すれば、数万円~十数万円の負担も珍しくありません(ケガの程度・治療内容で大きく変動)。
- 通院交通費:地味ですが積もります。公共交通機関を使えば数百円×回数、タクシーなら一気に跳ね上がる。
- 休業による収入減:有休でカバーできる期間を超えると、実入りが目減りします。経営者であれば、自分が動けない間の機会損失がさらに重い。
- 相手への賠償:歩行者や車と事故を起こした場合、**数百万円~**の賠償に発展することも。個人賠償の上限額が物を言います。
自転車通勤時の労災認定されるために気を付けたいこと
最後に、「認定されるために気を付けたいこと」を、自転車通勤ならではの視点でまとめます。ここを意識しておくだけで、いざというときの“説明力”と“証拠力”が段違いになります。
① ルートを“見える化”
普段の通勤ルートを地図アプリで保存・スクショ。雨天などで変えた日は、その理由(危険個所・工事・交通情報)もメモ。“なぜその道を選んだのか”を言葉にできるように。公式の定義でも合理的な経路かどうかが核心です。
② “最小限の立ち寄り”の意識
駅のトイレや日用品購入など最小限の行為は例外として許容される一方、店内に入り長く滞在して買い物――この線をまたぐと逸脱・中断に傾きます。店の敷地に入る=私的空間という裁判所の見立ては覚えておきましょう。
③ 事故直後の記録は“秒単位”
写真(現場・標識・信号・路面)、自転車の損傷、相手の連絡先・保険、目撃者の証言、警察への届出、診断書に“通勤中の自転車事故”と事情を明記。のちのち“合理性”を補強します。
④ 会社への即報告
「報告が遅れた」だけで不利になることは避けたいもの。当日中に上司・労務へ。必要書類の作成・監督署とのやり取りで、会社側の協力は大きな味方になります。
⑤ 安全装備と整備の“見える化”
ヘルメット・ライト・反射材・ベル、ブレーキ・タイヤ・チェーンの整備記録は**“過失を小さくする”材料**。安全配慮をしている人は、説明の説得力が段違いです。
そしてもう一つ。“選ぶ相棒”に保険がついているかも、実は大切です。傷害保険や後遺障害保険を備えたメーカー/ブランドを選べば、医療・収入・賠償の穴を埋める“初期装備”が手に入ります。日々のビジネスを止めないための、コストではなく“安心への投資”として考えてみてください。
例えば、当社の場合は三井住友海上火災保険と提携し盗難補償に加えて、傷害保険や後遺障害保険を提供しています。
まとめ
自転車通勤中の事故でも、通勤災害として労災認定される条件を満たしていれば補償を受けることが十分に可能です。最新データからも、事故は多く起きているが制度は整備されつつあり、申請の要件や証拠が整えば認定の見込みがあります。万が一認められなかった場合でも、健康保険や任意保険などを使って備えておくことができ、日頃からの準備が後に大きな差を生みます。自転車通勤を選ぶことは自由と便利さ、健康の利点を持っており、しっかり備えていけばリスクをぐっと減らせます。安心して自転車を走らせてください 😊

日本の次世代電動自転車を開発・販売する『MOVE』では日々通勤や趣味で自転車を利用する方・これから検討しようとしている方に向けて役立つ情報をお届けしています。主に「通勤・サイクリング・便利グッズ・運動利用」などニーズに合わせて専門的な知識をもったライターが集まる編集部が執筆しています。ぜひ記事を参考にライドライフをより深く楽しんでください。
-

New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!
2025.10.21- electric-bicycle-features
電動アシスト自転車を検討している方へ
-

New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!
2025.10.15- electric-bicycle-features
ebikeミニベロでも80Km移動が可能!?坂道も楽!?
-
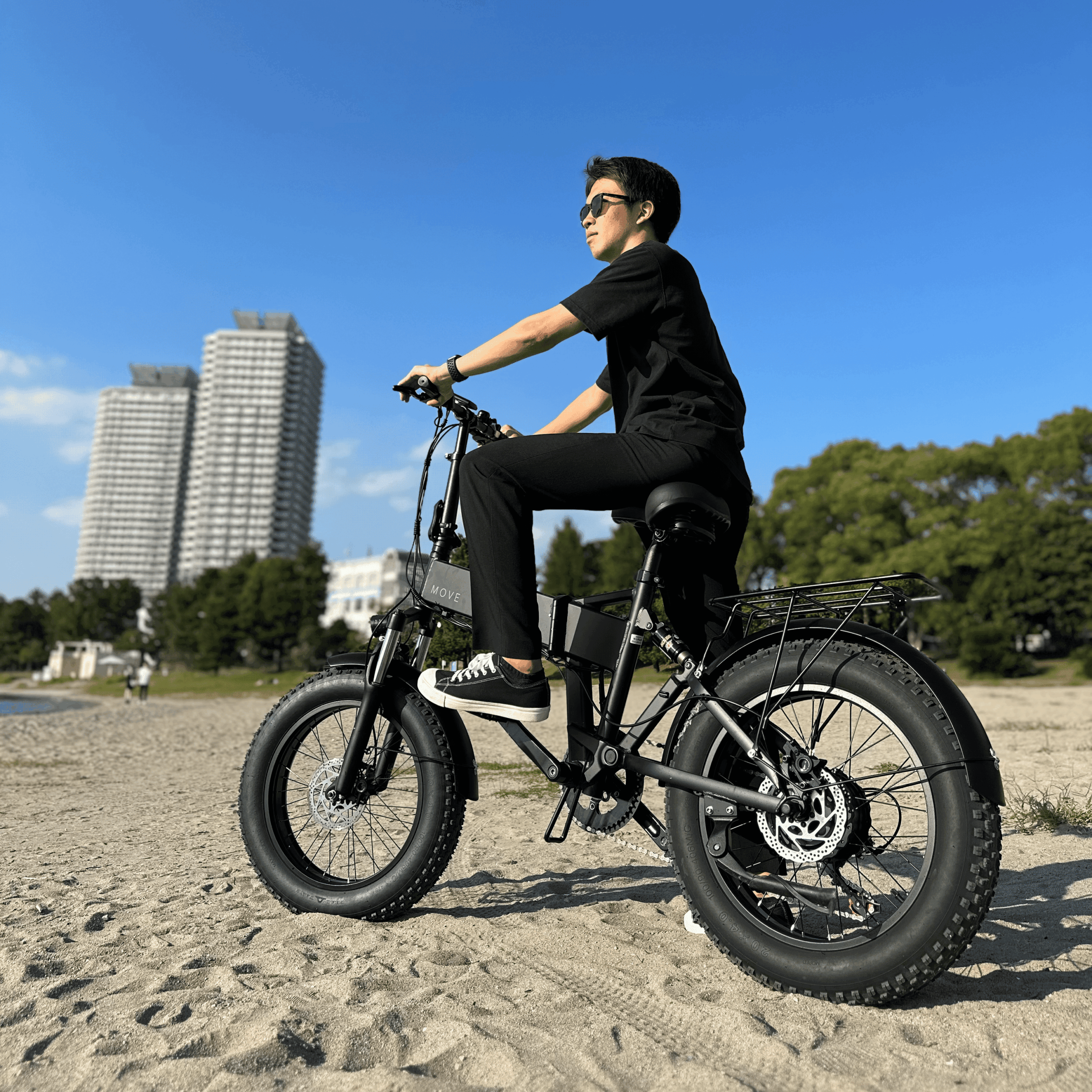
New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!
2025.10.12- cycling-benefits
- where-to-cycle
- beginner-cycling
<サイクリングを始める方のための完全ロードマップ>
-

New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!New Article!
2025.10.08- dissatisfaction-with-commuting-means
自転車通勤に変えたら交通費が支給されないなら逆に損?
















